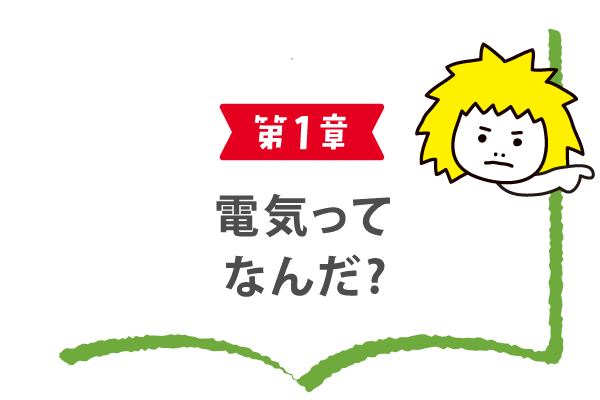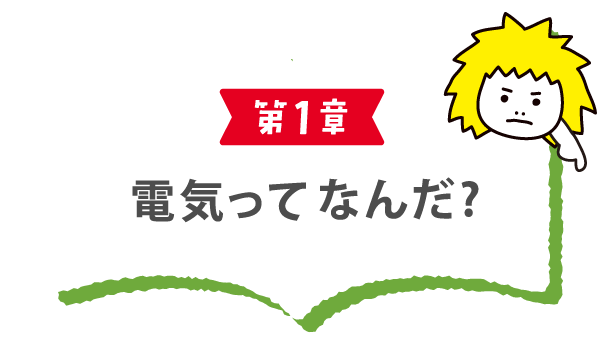電気の利用(日本)
日本で初めて電気の明かりがともったのは明治時代のこと。
やがて日本各地に広がり、
多くの人が電気を利用できるようになりました。
日本での電気利用の歩みを調べてみましょう。
日本で初めてアーク灯がつく
明治時代に、日本は西洋の技術を積極的に取り入れるようになりました。電気もそのひとつ。1878(明治11)年3月25日、イギリスの物理学者、エアトン教授の指導のもと、日本で初めてアーク灯がともされました。
アーク灯

提供:大成建設株式会社
2本の炭素棒の間を放電させることで光を放つようにした電灯。
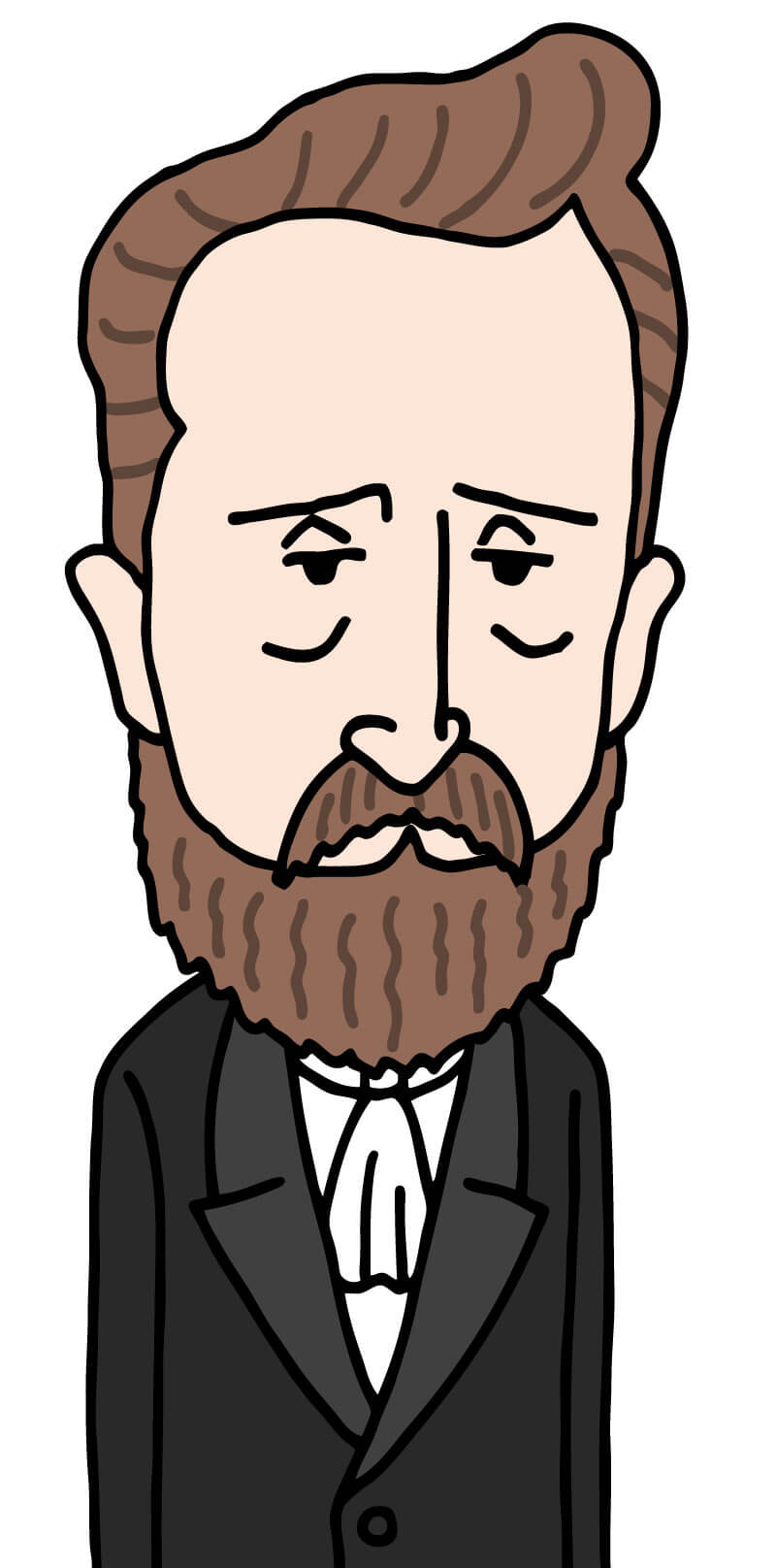
ウィリアム・エドワード・エアトン
(1847〜1908年)
イギリスから日本に招かれ、5年間指導した。

日本で初めて
電気の明かりがともった
3月25日は、その後
「電気記念日」になった。
銀座にアーク灯を設置
1882(明治15)年、東京の銀座に、アーク灯が設置されました。これが、人々が目にした初めての電灯です。それまでのガス灯や石油ランプよりも明るく、大勢の人々が見物に集まったそうです。
このアーク灯は、東京電灯株式会社(東京電力の前身)の発起人のひとりだった大倉喜八郎の発案で、多くの人に電灯のよさを知ってもらう目的で設置されました。
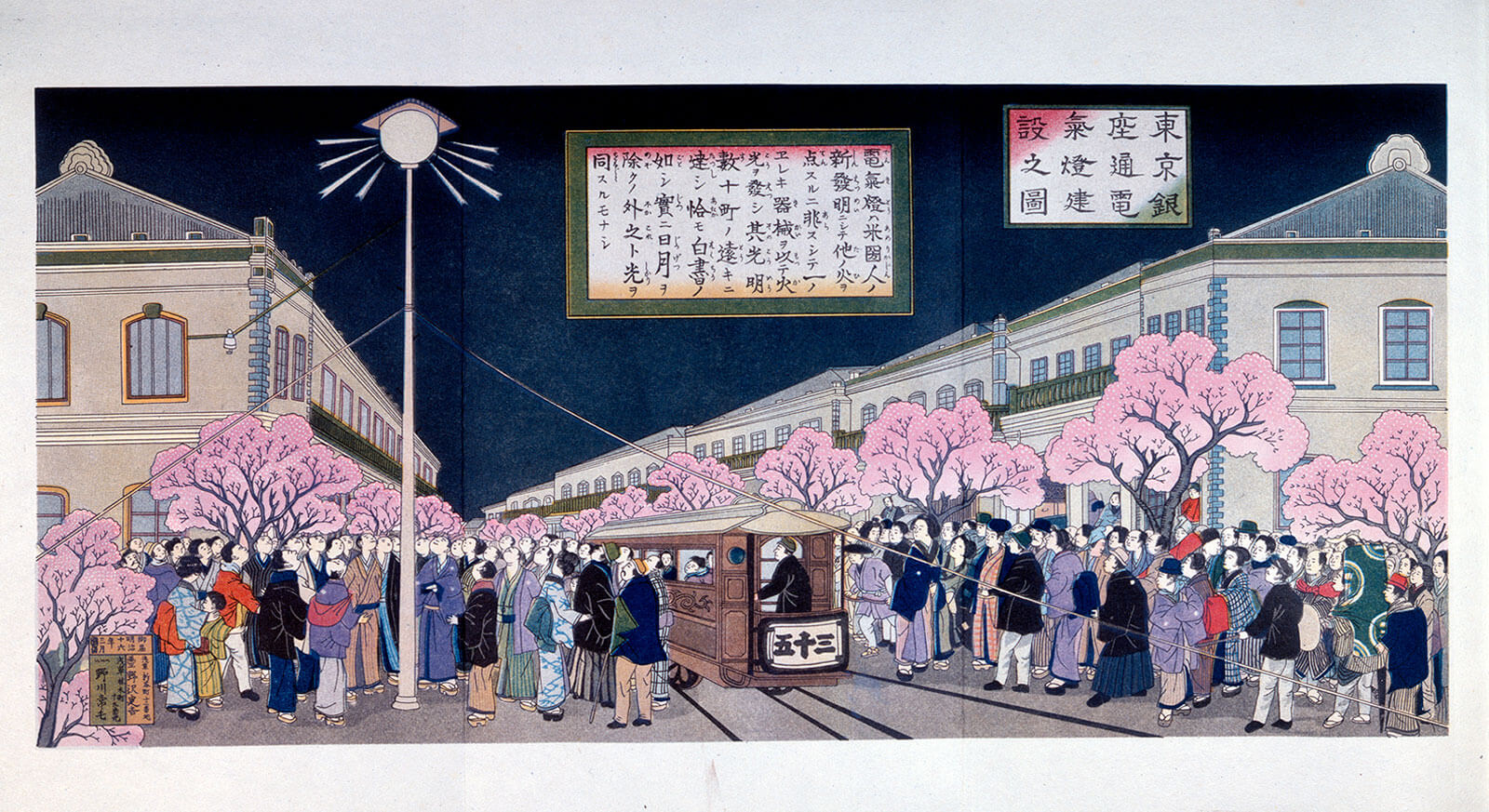
初めて設置されたアーク灯と、それを見物する人たち。アーク灯はアメリカから輸入されたもの。
このアーク灯は、
ろうそく2000本分の明るさだった。


よく見ると、
電線がえがかれているね。
各地に電力会社ができる
1886(明治19)年、日本初の電力会社として、東京電灯株式会社が開業しました。1887(明治20)年には日本橋茅場町に初めての火力発電所ができ、家庭への配電も行われるようになりました。この年には、名古屋電灯、神戸電灯、京都電灯、大阪電灯が相次いで設立され、その後、各地に電力会社ができていきました。

提供:電気の史料館
東京電灯の浅草発電所。1895(明治28)年に送電を始めた。
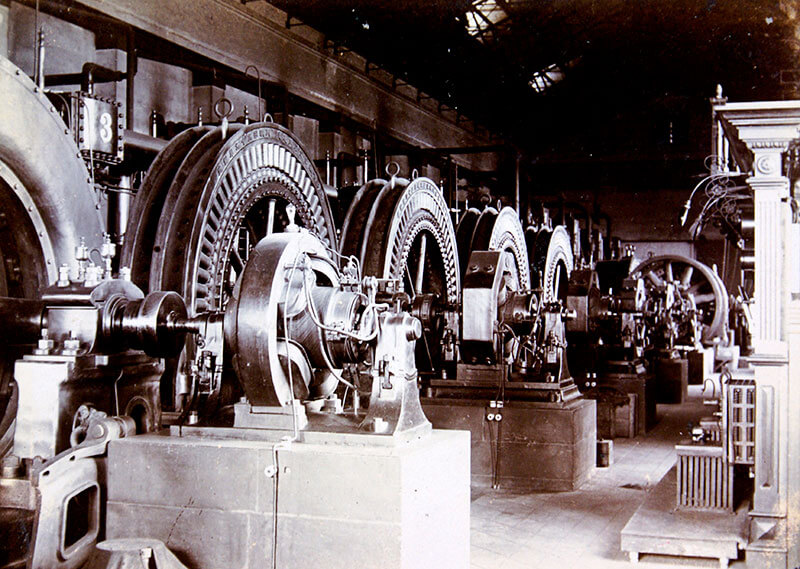
提供:電気の史料館
浅草発電所に設置された大容量の国産の発電機。

最初は、
明かりをともすために
電気が利用されていた。
四国に初めて電気が
日本各地に電力会社が設立されるなか、四国にも電力会社が誕生しました。1894(明治27)年、徳島電灯が設立され、翌年1月、徳島電灯の火力発電所でつくられた電気によって、四国で初めて、徳島県に電灯がともりました。
その後、徳島電灯は、このほかに四国各地で誕生した電力会社とともに、現在の四国電力につながっていきました。
四国の電力事業の歩み
年代 |
できごと |
|---|---|
1894 |
徳島電灯が設立される |
1895 |
徳島電灯が火力発電所を設置し、徳島県に電灯がともる(1月9日) |
1898 |
高知市に建設された火力発電所により高知県に電灯がともる(4月11日) |
1903 |
伊予水力電気の水力発電所により愛媛県に電灯がともる(1月17日) |
| 〜 | 〜 |
1939 |
電力事業が日本発送電に統一される |
1951 |
四国電力株式会社が設立される |

設立したころの徳島電灯